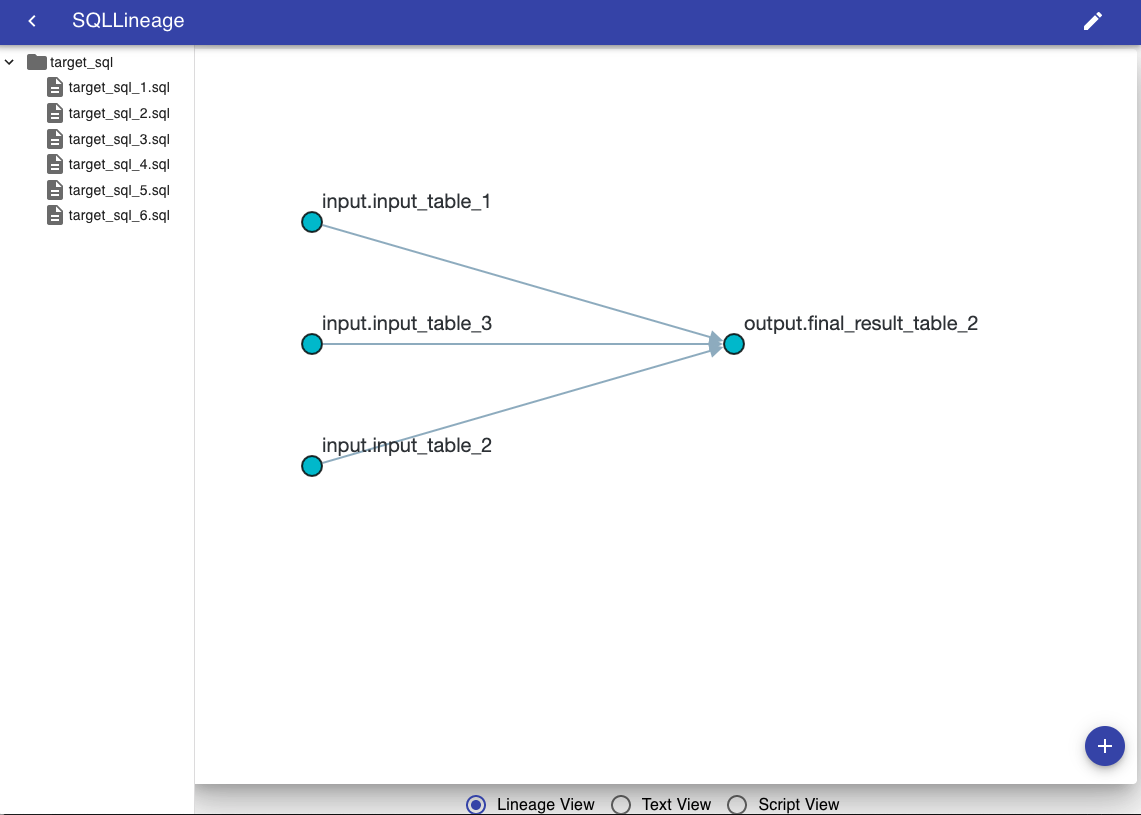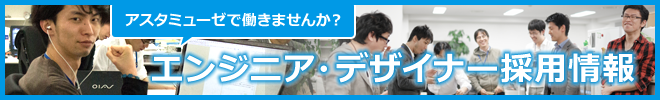大変ご無沙汰しております。じんと申します。テック・ブログの担当と相成りまして、今回は技術の裏側の思想について考えてみたいと思います。
今回の主人公は堀栄三という人です。詳しくはウィキペディアを参照していただければと思いますが、戦中から戦後にかけて優れた情報分析者として足跡を残しました。彼の著書に『情報なき国家の悲劇 大本営参謀の情報戦記』というものがあります。これはデータに関わる技術者の必読書としてもいいのではないか、とも思われるもので、昔からの愛読書の一つです。
本書は一読するたびに大きな学びがあり、その感想は到底ここで書き尽くせるものではありませんが、今回取り上げてみたい問いは以下のようになります。それは「どうすれば堀栄三のような優れた分析者が生じうるのか?」というものです。これは自分自身が彼のような精密な分析能力をどのようにすれば得られるのか、と考える面もありますし、彼のような分析者をどのように育成できるのか、と考える面もあります。
様々な要素があり、天賦の才というものもあるでしょうし、彼の父が陸軍の幹部であったことも大きな要素として働いているように思えます。一方、彼自身が言及しているように、彼自身が異なる分析姿勢を横断的に経験している点が非常に重要な要素として抽出できるのではないか、と考えるようになり、しばらくそれを整理していました。本書では、大きく3カ国の対する諜報が俎上に上げられています。米国、ソ連、そして当時の同盟国であるドイツです。
大前提として、堀は「情報の究極は権力の中枢から出てくる」と断言しています。権力とはすなわち意思決定の主体ですから、その意思がすなわち情報に他ならず、彼のこの考えは正鵠を射たものと言えましょう。
さて、まずドイツですが、当然、同盟国ですので、情報は比較的入手しやすいものです。ドイツの場合、当時の駐独大使などが、政権内部の要人に対して直接的に聞き取りを行うことができます。すなわち「人」を経由して情報が入ってきます。詳細な情報を得やすい一方、当該情報は同盟国ということもあり、なんらかのバイアスが含まれる危険性があります。一言でいいますと、「盛ってある」可能性が大きいわけです。また、同盟国であるため、どうしてもドイツから提供される情報を心情的に信用しやすくなってしまいます。
次にソ連です。当時は日ソ中立条約下にありますが、ソ連は日本の同盟国ドイツと死闘を繰り広げているなかでもあり、ソ連への諜報はとても難しいものでした。到底要人への聞き取りなど不可能です。したがって、新聞記事、雑誌をはじめとした報道、シベリア鉄道の貨物輸送量、要人の発言内容の過去と現在の違いなど、入手可能な情報を細かく積み上げ、それを多面的に分析していきます。また、当時の陸軍の仮想敵国はそもそもソ連でしたから、ソ連課のアプローチは、相手を端から信用していません。常に情報を疑っています。そのため、精度の高い情報を得るために、様々なデータの収集に余念がありません。ソ連の場合、「データ」を経由して情報を入手していたと言えるでしょう。
最後に米国です。米国に対しては既に開戦していましたから、ソ連と同様に、ドイツのように要人に直接聞き取りを行うことなどはできませんし、ソ連以上に情報収集は難しくなります。さらに状況が悪いことに、当時の陸軍は対ソ戦を重視していましたから、米国に対する分析は不十分なものでした。そこで、当時の堀の上司であった米国担当の杉田大佐は、米国担当を命じられた彼にさっそく現地の様子を見てくるように命じます。彼は驚愕しつつも、ニューギニアのウェワクに出張し、そこで現地司令官の寺本中将から現地の様子を詳しく聞き取ります。ウェワクに到着したまさにその日に彼は早速空襲に晒されます。これはまさに「現場」経由で情報を入手していると言えるでしょう。
まとめると以下のようになるかと思います。

堀自身は上司を「親方」、自分を「職人」と書いています。優れた複数の親方から、様々な分析手法を吸い上げ、それを実践、それどころか実戦で磨き上げたことが冒頭の問いへの一つの回答となるでしょう。おそらくこのなかの一つでも欠いたら情報参謀・堀栄三は完成しなかったでしょう。「人」と「データ」だけでは生々しい「現場」はわからず、「人」と「現場」だけでは俯瞰的な「データ」はわからず、「データ」と「現場」だけでは枢要な「人」はわかりません。
東京に戻った堀は様々な情報源から収集した情報を多角的に分析していきます。収集した情報を基に対米戦における基本的な戦術を確立させ、南方戦線に抽出される関東軍部隊に対して対応方針を教授します。この米軍の上陸作戦に対する対応方針は驚嘆すべきもので、データに基づく上陸前の空襲の分類、実際的な数字に基づく彼我戦力の比較など、何やら学術論文を読むような思いがあります。何よりも、彼は『敵軍戦法早わかり』という冊子によって対応方針、すなわち結論を導き出しています。彼は単なる分析者ではなく、体系的な方針を組み立てることができたのでした。
フィリピンでの決戦が近づくなか、堀はフィリピンの山下将軍の情報参謀としてマニラに向かいます。その間、台湾沖航空戦での誤った戦果発表を指摘したものの、それに伴う戦略の誤った変更を止めることはできませんでした。後世から見れば失敗を繰り返していく軍のなかで、堀は山下将軍を補佐し、最善を尽くします。レイテ島で敗北を喫したのち、ルソン島の山下将軍に殉じる覚悟であった堀は、東京に送り返され、本土決戦に向けた諜報に粉骨砕身します。その結果は後世の我々には明らかですが、彼の努力には感銘を受けざるを得ません。
とまれ、データ・サイエンスというものを、一定の規模のデータから何らかの価値、究極的には意思決定をもたらすものであるとすると、常に、そのデータは信用できるのか、意思決定に必要なデータを集め切れているのか、という懸念が生じます。私自身も十分なデータを集め切れているのか、と懸念を感じることが多々あります。これに対して堀は明快に回答しています。
コンピューターが出来て、もうそんな事態はあり得ないと思う人もいるだろうが、今度はインプットするデーターが百パーセント揃っている保証がない。〇・〇一パーセントでも誤差があれば、株式相場のブラックマンデーは必ず起ることになる。
ーー堀栄三. 情報なき国家の悲劇 大本営参謀の情報戦記. 文春文庫, 1996年.
戦後、警察予備隊が陸上自衛隊に改組されて間もない1956年、スエズ動乱が発生します。陸上自衛隊に参画していた堀は、冷戦下にあった米ソの全面衝突の可能性について上司から見解を求められます。堀の判断は「衝突には至らない」というものでした。この判断は堀の上司が上司自身の見解として提出しなければなりません。顧問会議などを作り、その責任の所在を曖昧にしたい、とこぼす上司に堀は冷然と言い放ちます。
「顧問を作っても同じですよ、情報の判断には、百パーセントのデーターが集まることは不可能です。三十パーセントでも、四十パーセントでも白紙の部分は常にあります。この空白の霧の部分を、専門的な勘と、責任の感とで乗り切る以外にありません」
ーー堀栄三. 情報なき国家の悲劇 大本営参謀の情報戦記. 文春文庫, 1996年.
何らかの判断のために情報を収集し、見解を提示する仕事をここしばらく多く行っています。誤った判断は組織に惨禍をもたらし、その可能性を考えるとこれは必ずしも気安い作業ではありません。そんなとき、常に彼のことを考えています。最後にまた冒頭の問いに戻ります。幽明相隔てた彼に直接尋ねることはできませんが、熱心に本書を読み返し、彼の思考を辿り、現代の「データ・サイエンス」を踏まえて、彼に「どうすればあなたのようになれますか?」と尋ねてみます。彼は冷然と一言、言い放つのではないか、と想像しています。「顧問」を「ビッグ・データとAI」と置き換えて。
しかし、0.01%の誤差まで努力した結果は無駄ではない、専門家としての矜恃と責任感を持つ限り、と彼は付け加えます。その時の彼は、私の覚悟を問うように、冷厳に私の眼を見据えています。
データの収集と解析、分析は重要です!アスタミューゼ株式会社ではエンジニアを募集しています!ひりつくようなデータエンジニアリングやデータサイエンスに対して、我こそは、という方からのご連絡をお待ちしております。